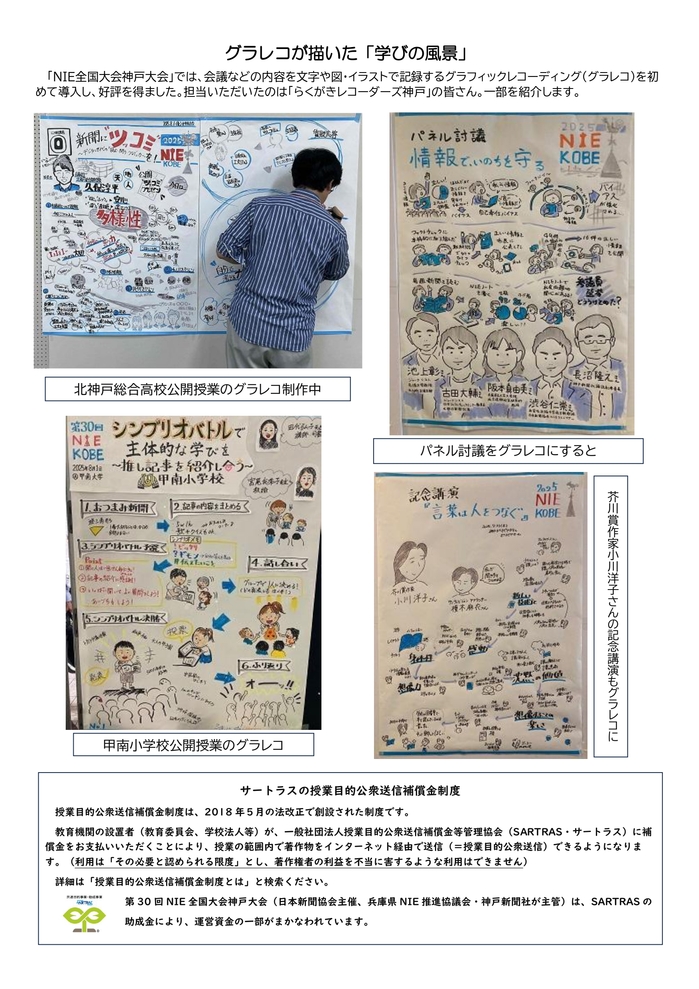社会とつながり、生徒を支える力に
幅広い読者を想定した紙面づくりを目指している。難しい漢字にはルビを振り、「記事は短く、分かりやすく」と現場の記者に求めている。そんな新聞を特別支援学校ではどんなふうに活用しているのか。聞いてみたくなり、兵庫県立のじぎく特別支援学校(神戸市西区)の実践発表の講評に手を挙げた。
担当の藤本友美教諭(現・兵庫県立上野ケ原特別支援学校教頭さくら訪問学級担当)は2年間のNIE実践を「スモールステップで進めることに注力した」と振り返りつつ、生徒たちの興味・関心がより広く、より深くなっていく過程を紹介した。
授業の進め方を聞くと、新聞との関わり方に工夫が凝らされていることがよく分かる。まず1年目の「(1)新聞を見よう」と「(3)ニュースを知ろう」は、読者の目線で新聞と触れる内容だ。続く「(2)わからないことを聞こう」や「(4)気になるニュースを伝えよう」は記者の視点に近い。興味のあるニュースを選び、その理由について考えることは、どんな取材を進めるのかにも通じる。
さらに「(5)新聞をつくろう」と2年目の実践は、新聞発行の作業であり、レイアウトや見出し(タイトル)を考える整理部門の視点が必要になる。「見る・知る」から「聞く」「伝える」「つくる」までを連続して学ぶことで、これまでとは違ったニュースの読み方や、批判的な視点も身につくのではないか。
会場には、藤本先生を編集長に生徒たちが手がけた「給食新聞」が貼り出されていた。目を引いたのは「どうしてオムライスの時にケチャップがないのですか」という栄養教諭への質問だ。学校生活で感じた疑問を尋ね、答えを記録し、記事にして伝える。「学校で使える塩の量が2.5㌘と決まっているから。ケチャップを使うと塩分の取りすぎになる」という回答を引き出した生徒は納得した様子だったといい、ケチャップのかかっていないオムライスに疑問を感じていたほかの生徒にも大きな反響をもたらしただろう。
新聞社側からはウェブ記事の活用を提案したい。各社のウェブ版には、紙面よりも詳しい記事やウェブのみのコンテンツが揃う。紙面のようにスペースの制約がなく、複数の関連写真が掲載されることも多い。動画コンテンツを見れば、音と映像で現場の様子が伝わり、データベースの検索機能によって紙面で読み落とした記事にも出合える。ウェブ情報の活用によって、さらに深くニュースに触れることができ、紙の新聞にとどまらず「スマホなどを使って正しい情報を得る」という、初日のパネル討議の提案にも合致している。
藤本先生は、授業を通じて新聞と能動的に向き合うようになった生徒たちに触れ、発表をこう締めくくった。「NIEの実践を通じて身につけた『見る・聞く・知る・伝える・つながる力』は、必ずやこの先、生徒たちが生きていく上で彼らを支える力となると確信している」。新聞の役割を改めて自覚し、作り手としてこちらの背筋が伸びる報告だった。
三木良太(神戸新聞社報道部長)(8月27日)
 [写真説明]「スモールステップで進めてきた」。特別支援学校のNIE実践発表は示唆に富んでいた=8月1日、神戸市東灘区岡本8、甲南大学岡本キャンパス
[写真説明]「スモールステップで進めてきた」。特別支援学校のNIE実践発表は示唆に富んでいた=8月1日、神戸市東灘区岡本8、甲南大学岡本キャンパス
.

 渋谷仁崇主幹教諭による公開授業のテーマは「新聞から考える、いのち輝くまちづくり」。3年生が各自の「NIEノート」に貼った切り抜き記事や書きためた感想をもとに、災害、熱中症、ジェンダー平等などの社会課題について意見を発表した。自分ごととして捉えているかがポイントだ。
渋谷仁崇主幹教諭による公開授業のテーマは「新聞から考える、いのち輝くまちづくり」。3年生が各自の「NIEノート」に貼った切り抜き記事や書きためた感想をもとに、災害、熱中症、ジェンダー平等などの社会課題について意見を発表した。自分ごととして捉えているかがポイントだ。 公開授業では、東日本大震災を扱った異なる新聞記事を読み比べ、その内容の違いから、発信者の思いや意図を探った。同一の震災を取り上げた記事でも、地域や時期によって焦点が異なる。比較することで違いが浮き彫りとなり、子どもたちは情報の背景にある発信者の思いなどを推し量ることができた。
公開授業では、東日本大震災を扱った異なる新聞記事を読み比べ、その内容の違いから、発信者の思いや意図を探った。同一の震災を取り上げた記事でも、地域や時期によって焦点が異なる。比較することで違いが浮き彫りとなり、子どもたちは情報の背景にある発信者の思いなどを推し量ることができた。 俳句の町・松山からの参加ということで、分科会第2部、姫路市立飾磨中部中学校の実践発表「NIE俳句~記事の写真から豊かにイメージしよう~」の講評を担当させていただいた。
俳句の町・松山からの参加ということで、分科会第2部、姫路市立飾磨中部中学校の実践発表「NIE俳句~記事の写真から豊かにイメージしよう~」の講評を担当させていただいた。