
兵庫県NIE推進協議会は、第4回NIE(教育に新聞を)「わたしの推し記事」コンクールを開催します。
対象は、小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の児童・生徒の皆さんです。
新聞のなかから興味のある「推(お)し記事」を見つけて切り抜き、他の人に薦めたいほどその記事に魅力を感じるのか、その記事を人々が広く知ることで、世の中にどんな変化があると思うかを600字以内で書いて、記事と一緒に送ってください。
締め切りは2026年4月30日必着、結果は同年7月に新聞紙上、本協議会ホームページで発表します。
応募方法は、下記の応募用台紙に記載の応募要領、概要のページをご参照ください。
台紙は、直筆用とパソコン入力用の台紙の2種類から選べます。どちらもダウンロードできます。いずれも応募は印刷して提出してください(データでの提出は不可)
たくさんのご応募をお待ちしております。
●応募する児童・生徒の皆さんへ
【直筆用台紙】
A3判(※)=1枚、または、A4判=3枚 のどちらか
(A4判は左上を綴じてください)
(※)A3判は印刷設定で「両面印刷、短辺とじ、用紙サイズA3」を指定してください。モノクロ印刷可。
直筆台紙は濃く、分かりやすく記入し、所定の場所に選んだ「推し」の記事を貼ってください。
【パソコン入力用台紙】
①個人票Word=A4判
(個人情報を入力してから印刷し、裏面に選んだ「推し」の新聞記事を貼ってください)
②作文台紙Word=A4判
(600字=1枚半まで。作文を直接入力したあと印刷してください)
応募は①と②を綴じてください。モノクロ印刷可。
●学校の先生へ
概要 学校応募用紙Word
学校応募用紙はダウンロードして入力できます。1校につき1枚、必ずお送りください。
「安全にダウンロードすることはできません」と表示された場合の操作手順はこちら
上記の方法でダウンロードできない場合は、お手数ですが推進協議会(hyogo-nie@kobe-np.co.jp)へお問い合せください。

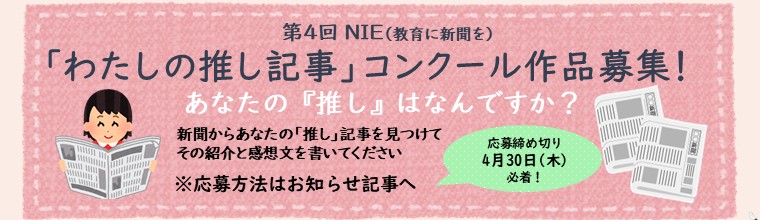
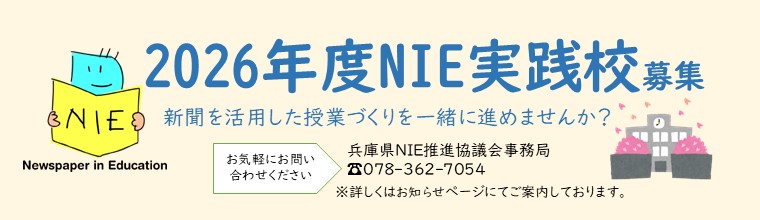

 神戸新聞記者が講師に
神戸新聞記者が講師に